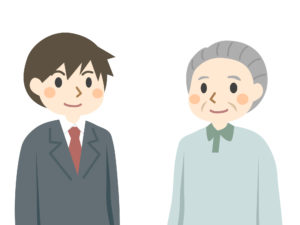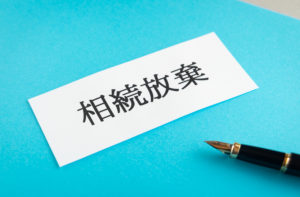贈与税の税制改正

令和5年度税制改正により「歴年課税における相続開始前の贈与」と「相続時精算課税制度」の見直しが図れ、
令和6年1月1日以後の贈与に摘要されることになります。
両者の改正ですが、歴年課税の改正は相続税の累進負担の回避防止の改正になります。
一方で、精算課税については高齢世代から若年世代への資産移転を促すため使い勝手をよくした改正になります。
1 歴年贈与
歴年課税による相続財産への加算期間の延長については、相続開始前の駆け込み贈与による相続税の回避の防止を目的としております。
歴年贈与で贈与を行って、相続が発生した場合、死亡日から一定期間さかのぼって相続財産に加算されます。一定期間については、改正前において3年でしたが、改正後は7年になりました。
これによって相続前の贈与による節税について、改正前より制限されることになりました。改正は令和6年1月1日からスタートですが、相続財産への加算の拡大については段階的に摘要される形になります。具体的には令和6年1月1日から令和8年12月31日までに発生した相続については、相続財産への加算は7年ではなく3年であり、令和9年1月1日から令和12年12月31日までに発生した相続について、段階的に拡大期間が延びていき(加算対象期間:令和6年1月1日から相続開始日)、最終的に令和13年1月1日の相続から7年になります。
なお、緩和措置として、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については100万円を控除した残額について加算されることになります。
2 相続時精算課税制度
(1)改正前の制度について
相続時精算課税制度についてですが、まず贈与時に財産額から2,500万円を控除して、うわまわった金額について20%の税金を納めます。相続の発生時の相続税の計算においては、過去に贈与した財産が全額加算され、計算された相続税から、過去に支払った贈与税を精算する制度です。
高齢世代から若年世代への資産移転を促す目的に設けられた制度ですが
いったん精算課税制度を利用すると、少額の財産を贈与した場合も相続時に相続財産へ加算されるため、使い勝手が悪くなかなか利用が進まない状況でした。
(2)改正について
使い勝手をよくするため、110万円の基礎控除を設けて、110万円以下であれば申告も不要としました。
(3)計算例
初年度に3,000万円贈与して5年後に100万円贈与
(a)初年度の贈与
(3,000万円-110万円-2,500万円)×20%=78万円(納付税額)
(b)5年後の贈与
100万円<110万円 納付税額ゼロ、申告も不要
3 災害時の救済措置
贈与財産については、相続税において、贈与時の価格で評価されます。
これは、贈与後の価格変動リスクは受贈者が負うものと考えているためです。
しかし、災害など納税者の責めに帰すことができない事由により、資産の価格が著しく下落した場合は納税者を救済する措置が必要という観点から、災害によって一定の被害を受けた場合は、贈与時の価格から災害による被災価格を控除することが出来るようになりました。
4 まとめ
歴年課税は改正後、使い勝手が悪くなりました。一方で精算課税は使い勝手が良くなりました。但し、どちらを利用するのがよいかについては、状況によって変わってきます。
例えば毎年110万円以下で贈与するのであれば、相続前7年の遡りがない精算課税が歴年課税より有利かと思われます。
一方で相続税率が最高税率であるため、相続税率より低い水準の贈与税を払った方が有利な富裕層の場合は、依然として歴年課税の方が有利かと思われます。納税者の個別の状況に応じて、どちらを利用するか判断するのが重要となります。
(注)当コラムは一般的な情報提供の趣旨で記載しており、具体的事案に対する法的アドバイスではございません。法律・判例は将来において改正・変更の可能性がございます。また、当コラムにおいては読みやすさ・わかりやすさを重視しており、厳密な意味での正確性を犠牲にしている箇所もございます。ご了承ください。
6 事務所紹介

代表弁護士 家村 邦雄
石神井法律事務所は東京都練馬区石神井町で相続・遺言等の業務を取り扱っている法律事務所です。
遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・遺言・成年後見等について弁護士が対応致します。
代表弁護士の家村邦雄(東京弁護士会所属)は宅地建物取引士の資格も有しており、不動産相続を得意としている相続弁護士です。
事務所での初回のご相談(30分)は無料です。練馬区内出張相談もおこなっております。 西武池袋線石神井公園駅徒歩3分。練馬区石神井庁舎の斜め向かい。土曜日も営業。お気軽にご相談ください。