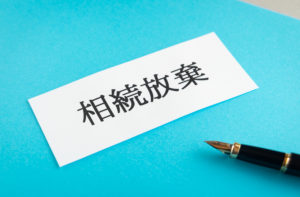成年後見
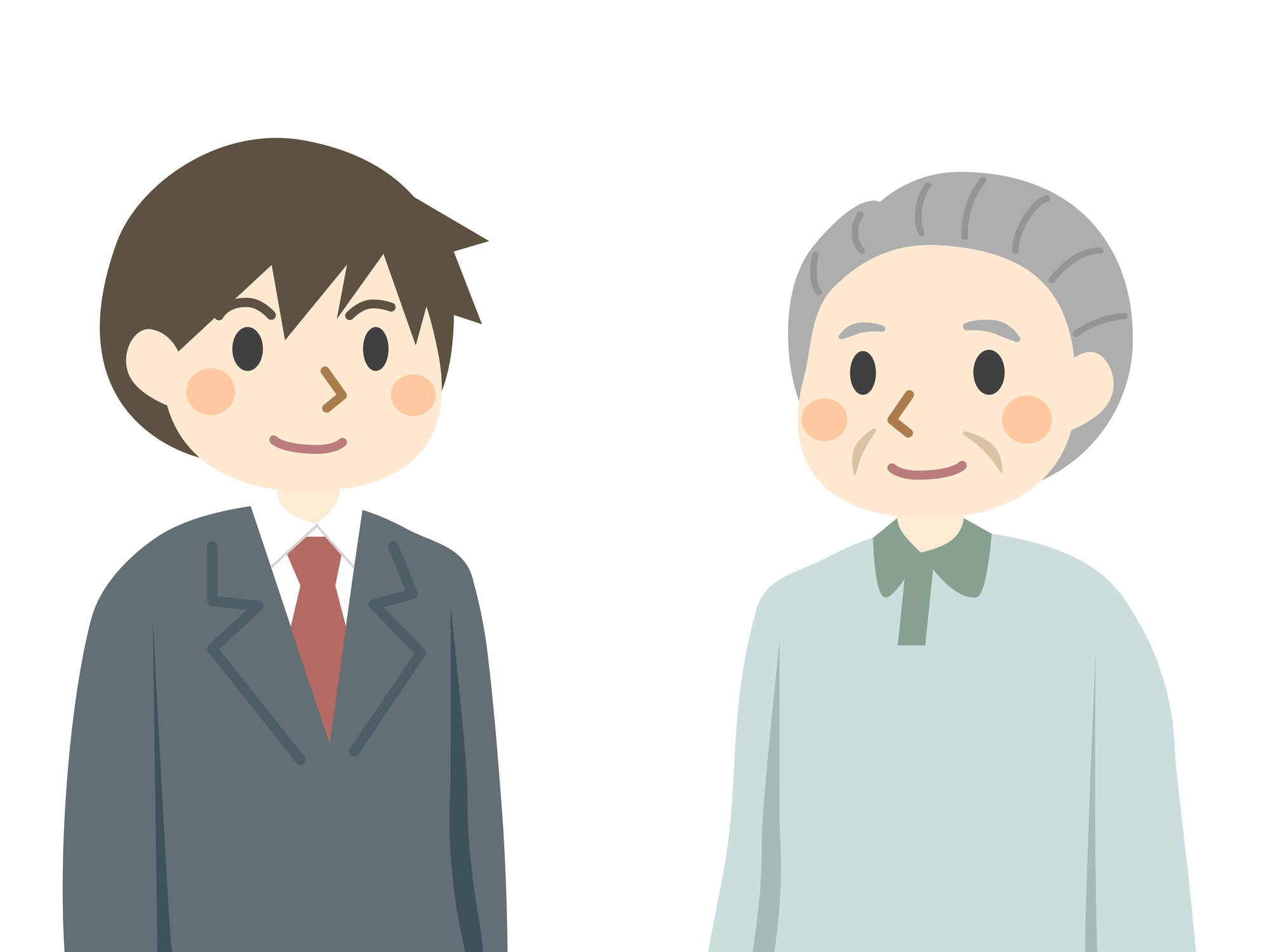
1 成年後見とは
成年後見制度は、判断能力が十分でない方を保護するための制度で、その中には、後見・保佐・補助・任意後見があります。
それぞれが対象としているのは以下のような方です。
後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方
任意後見:本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。
本コラムでは、この中でも一番利用が多い後見について解説していきます(以下では、後見と同じ意味で成年後見という言葉を使用しています)。
介護契約の締結や不動産の売却といった場面で成年後見が使用されます。
2 成年後見の申立て手続き
それでは、成年後見の申立て手続きについて説明していきたいと思います。
まずは、申立ての手続きをできるのは誰か列挙していきます。以下の方々が申立てをおこなうことができます。
・本人(後見開始の審判を受ける者)
・配偶者
・四親等内の親族
・未成年後見人
・未成年後見監督人
・保佐人
・保佐監督人
・補助人
・補助監督人
・検察官
・任意後見契約が登記されているときは、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。
成年後見人には親族の方も選任されることができますが、令和3年のデータによると(成年後見人だけでなく保佐人、補助人も含むデータですが)、親族が成年後見人等に選任されているのはおよそ20%です。のこりのおよそ80%は、弁護士・司法書士等の親族以外の方が選任されています。
一方、以下のような方々は、成年後見人に選任されることができません。
・未成年者
・家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人
・破産者(復権していない者)
・本人に対して訴訟をしている(した)者並びにその配偶者及び直系血族、
・行方不明者
申立ては原則として、ご本人の住民票のある住所地を管轄する裁判所におこないます。
東京23区と島しょ部の場合は、東京家庭裁判所の本庁(霞が関にあります)
それ以外の東京都の場合は、東京家庭裁判所の立川支部
になります。
標準的な添付書類は以下のとおりです。
・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)
・本人の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
・成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
※ 成年後見人等候補者が法人の場合には、当該法人の商業登記簿謄本(登記事項証明書)
・本人の診断書(発行から3か月以内のもの)
・本人情報シート写し
書式等については裁判所ホームページに記載があります。
・本人の健康状態に関する資料
介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳などの写し
・本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)
東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局で発行するもの。
・本人の財産に関する資料
・預貯金及び有価証券の残高がわかる書類:預貯金通帳写し、残高証明書など
・不動産関係書類:不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など
・負債がわかる書類:ローン契約書写しなど
・本人の収支に関する資料
・収入に関する資料の写し:年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、家賃、地代等の領収書など
・支出に関する資料の写し:施設利用料、入院費、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書など
成年後見の申立てをおこなうとその取り下げには裁判所の許可が必要になります。
成年後見人の候補者が選任されそうにないという理由では取り下げはできませんので、注意が必要です。
また、選任された成年後見人等に関して不服申し立てはできませんので、こちらも注意が必要です。
3 成年後見人選任後
成年後見人の業務の内容としては以下のようなものが挙げられます。
(以下の記載は弁護士が成年後見人に選任されたことを想定した記載です。)
・各種契約 介護サービス、入院契約等
・各種支払 入院費、家賃等
・行政手続 各種申請(助成金、還付金、介護認定等)
・不動産管理 支援者や専門家に依頼可
・確定申告 専門家に依頼可
・裁判所への報告・必要に応じて許可申立て(居住用不動産の売却、賃貸、賃貸借契約の解除、抵当権設定等)
4 成年後見の費用と申立てから審判までの時間
申立手数料 800円
登記手数料2600円
送達・送付費用としてあらかじめ納める切手 3270円分
鑑定費用は10~20万円(鑑定は実施されないこともあります。)
申立代理人弁護士費用 27万5000円(税込)(当事務所における2023年8月時点の金額です。)(この弁護士費用は本人(成年被後見人)の財産からは支払われないので注意が必要です。)
東京家庭裁判所が公表している通常の後見事務(成年後見監督人の場合は、後見監督事務)をおこなった場合の
成年後見人の報酬の目安は、月額2万円
(ただし、管理財産額が1000万超~5000万円以下の場合、月額3~4万円
管理財産額が5000万円超の場合、月額5~6万円)
成年後見監督人の報酬の目安は、管理財産額が5000万円以下の場合、月額1~2万円
管理財産額が5000万円超の場合、月額2万5000円~3万円 です。
以上は成年後見人が弁護士等の専門職の場合の記載です。親族が報酬付与の申立てをおこなった場合は、上記の金額から事案に応じて減額されることがあるとのことです。
申立てをおこなってから審判(家庭裁判所の判断)がでるまでの期間は、1か月程度が多く、3か月以内でほとんどの判断がなされます。
5 弁護士に依頼するメリット
上記のように成年後見制度は複雑です。
弁護士に依頼すると、弁護士が申立書の作成と添付書類の取得をおこない、申立ての手続きがスムーズに進みます(一部ご依頼者にご用意をお願いする書類もございます)。
ご覧いただき、ありがとうございました。
当コラムをご覧になられて、成年後見の申立ての手続きを弁護士に依頼したいと思われた方は、お問い合わせフォームかお電話(03-6913-1420)にてご連絡ください。
(注)当コラムは一般的な情報提供の趣旨で記載しており、具体的事案に対する法的アドバイスではございません。法律・判例は将来において改正・変更の可能性がございます。また、当コラムにおいては読みやすさ・わかりやすさを重視しており、厳密な意味での正確性を犠牲にしている箇所もございます。ご了承ください。
6 事務所紹介

代表弁護士 家村 邦雄
石神井法律事務所は東京都練馬区石神井町で相続・遺言等の業務を取り扱っている法律事務所です。
遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・遺言・成年後見等について弁護士が対応致します。
代表弁護士の家村邦雄(東京弁護士会所属)は宅地建物取引士の資格も有しており、不動産相続を得意としている相続弁護士です。
事務所での初回のご相談(30分)は無料です。練馬区内出張相談もおこなっております。 西武池袋線石神井公園駅徒歩3分。練馬区石神井庁舎の斜め向かい。土曜日も営業。お気軽にご相談ください。