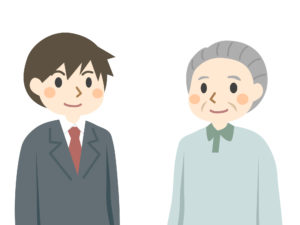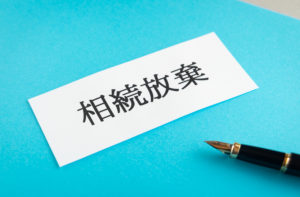相続登記の義務化

自己紹介
石神井法律事務所のコラムをご覧いただき、ありがとうございます。
石神井法律事務所は東京都練馬区石神井町で相続・遺言等の業務を取り扱っている法律事務所です。
遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・遺言・成年後見等について弁護士が対応致します。
代表弁護士の家村邦雄(東京弁護士会所属)は宅地建物取引士の資格も有しており、不動産相続を得意としている相続弁護士です。
事務所での初回のご相談(30分)は無料です。練馬区内出張相談もおこなっております。
西武池袋線石神井公園駅徒歩3分。練馬区石神井庁舎の斜め向かい。土曜日も営業。お気軽にご相談ください。
相続登記の義務化の内容
令和6(2024)年4月1日から相続登記が義務化されますが、その内容について本日は解説していきたいと思います。
分かりやすく書きますと、相続・遺言・遺産分割協議により不動産を取得した相続人の方は、所有権を取得したことを知った日(相続・遺言の場合)、または、遺産分割協議が成立した日(遺産分割協議の場合)、から3年以内に登記の申請をしなければならなくなるということです。
登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれており、この所有者不明土地の解消のための法改正です。
相続登記が義務化されるのは、令和6(2024)年4月1日からですが、それ以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので、注意が必要です。
義務化以降、相続登記をしないとどうなるのか
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、正当な理由としては、相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合などが考えられます。
なお、過料は、「かりょう」と読みますが、これは罰金等とは異なり、犯罪に対する刑罰ではありません。したがいまして、過料が科されても前科がつくわけではありません。
本日は、以上で終了です。
ご覧いただき、ありがとうございました。
当事務所では、相続登記のための遺産分割協議のご依頼にも対応致しております。
当コラムをご覧になられて、相続登記のための遺産分割協議について弁護士に相談したいと思われた方は、お問い合わせフォームかお電話(03-6913-1420)にてご連絡ください。
(注)当コラムは一般的な情報提供の趣旨で記載しており、具体的事案に対する法的アドバイスではございません。法律・判例は将来において改正・変更の可能性がございます。また、当コラムにおいては読みやすさ・わかりやすさを重視しており、厳密な意味での正確性を犠牲にしている箇所もございます。ご了承ください。なお、相続登記の手続きについては法務省のホームページに詳しい記載がありますので、ご自身で手続きをされる方はそちらを参照してください。